技能実習制度から何が変わる?新制度「育成就労」の全体像をわかりやすく解説
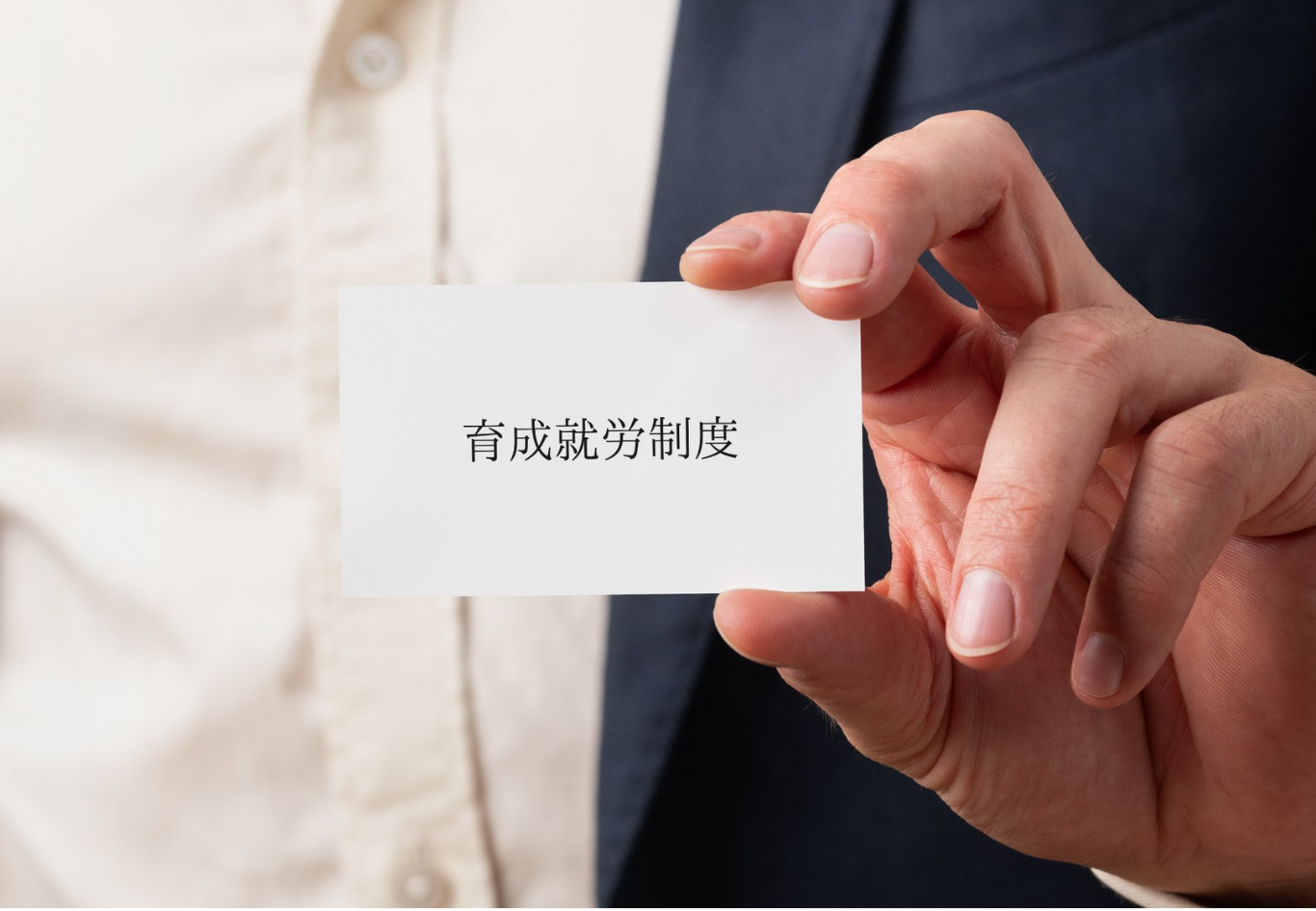
こんにちは!
行政書士事務所ビザハブの羽野です。
今回は、これまでの技能実習制度に代わって新たに創設される「育成就労制度」について、制度の目的や概要、送出しの仕組み、そして将来的なキャリアパスまで、丁寧に解説します。
「技能実習制度との違いがよく分からない…」
「外国人材を受け入れたいけど、制度が変わるって本当?」
「育成就労から特定技能へ移行できるって聞いたけど、条件はあるの?」
などなど、制度の変更に伴って疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、「育成就労制度」とは何か、制度の目的や仕組み、特定技能との関係性などをしっかりと理解できるはずです。
 羽野
羽野この記事は以下のような方におすすめ!
・外国人材の受入れを検討している企業・団体の方
・新制度「育成就労制度」の目的や流れを具体的に知りたい方
・技能実習制度からの移行について、正確な情報を知りたい方
育成就労制度は、国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、日本の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする制度です。
制度が本格的にスタートすれば、瞬く間に普及することが予想されます。現在、技能実習生や特定技能外国人を受け入れている事業者の方々は、今のうちに育成就労制度の内容をしっかり把握しておくことが重要です。
そこで、外国人関連の申請を専門としている行政書士の立場から、この新制度についてわかりやすくご紹介します。
1. 育成就労制度とは?
制度創設の背景と目的
「育成就労」は、これまで外国人材の受入れの主な制度であった「技能実習」に代わり、新たに創設される制度です。(令和6年6月21日に公布されており、公布日から起算して3年以内の政令で定める日に施行される予定です。つまり、遅くとも令和9年(2027年)6月21日までには施行されることになります。)
背景にあるのは、少子高齢化による深刻な人手不足と、技能実習制度が抱えてきた構造的な問題です。
技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」を建前としつつも、実態としては人手不足を補うための労働力確保手段として利用されてきました。
この建前と実態の乖離、転籍制限による労働者の拘束性、送出機関の不透明な費用構造など、多くの課題が指摘されてきたのです。
こうした状況を受け、政府は制度を根本から見直し、より実態に即した形で外国人材を受け入れるために「育成就労制度」を創設しました。
この制度では、**「人材育成」と「人手不足分野での就労確保」**という現実的な目的を明確に掲げています。
ポイントまとめ
- 旧制度の建前(国際貢献)→新制度の実態重視(人材育成・労働力確保)
- 外国人材を“育てて定着させる”という考え方に転換
- 企業と外国人の双方にとってメリットのある制度設計
育成就労制度は、外国人を単なる一時的な労働力として扱うのではなく、計画的に育て、戦力として共に働くための制度です。
その点で、受入れ企業にとっても中長期的な人材戦略の一環として活用が期待されます。
2. 技能実習制度との違い
何がどう変わったのか?
育成就労制度を理解するうえで、技能実習制度との違いを整理することは非常に重要です。
下記の表に、主な違いをわかりやすくまとめました。
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 国内の人手不足分野における人材育成・確保 |
| 在留資格 | 技能実習1号~3号(最大5年) | 育成就労(最大3年)→特定技能1号・2号へ移行可 |
| 転籍(職場の変更) | 原則不可(例外的対応のみ) | 転籍の制限緩和 |
| キャリアパス | 「帰国」が制度上の原則 | 特定技能1号への移行可、長期就労を推奨 |
| 支援団体 | 監理団体 | 監理支援機関 (許可基準は厳格化※1) |
| 送出機関の費用管理 | 不透明でトラブル多数 | 二国間取り決め(MOC)で手数料が不当に高額にならない仕組みの導入 |
可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。
ポイントまとめ
- 目的が現実に即した「労働力確保」に明確化されたことで、制度の使いやすさ・透明性が向上
- 二国間取決め(MOC)に基づき、費用構造の透明化・不当請求の抑制が図られている
- キャリアパス(特定技能への移行)がより明確になり、外国人本人にとっても将来を描きやすい制度に
育成就労制度は、単なる名称変更ではなく、**制度そのものの設計思想が大きく変わった「実質的な新制度」**です。
企業にとっても、制度の背景や違いを理解しておくことが、スムーズな導入と長期的な活用の鍵となります。
3. 育成就労制度のしくみと対象業種
どんな人が、どんな職種で働ける?
育成就労制度は、将来的に特定技能1号へと移行することを見据えた「育成型」の在留資格制度です。
制度の設計上、技能実習制度のような「名目上の研修」ではなく、実際の業務を通じて段階的にスキルと日本語能力を高めていくことが前提となっています。
制度の基本的な枠組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格の名称 | 「育成就労」〈新設〉 |
| 在留期間 | 原則として最大3年間 (試験に不合格の場合は最大1年間延長可能) |
| 対象業種 | 特定技能1号と一致させる |
| 家族帯同 | 基本的に不可 |
| 転籍(受入先の変更) | 転籍の範囲を拡大・明確化 |
| 制度のゴール | 特定技能1号への移行 (技能試験・日本語試験の合格が必要) |
受入企業は、育成就労者に対して「育成就労計画」(認定制)を策定し、監理支援機関とともに適切な教育・指導・支援を行います。
対象となる外国人
育成就労制度を利用できる外国人は、主に以下のような条件を満たす方が想定されています:
- 送出国と日本がMOC(二国間取決め)を結んでいること
- 日本語能力A1レベル以上(または相当講習でも可能)
- 18歳以上で健康であり、業務遂行が可能
- 犯罪歴などがなく、在留資格取得に支障がないこと
また、育成就労者が来日前に受ける講習や、企業・管理支援機関が提供する教育支援なども制度上整備される予定です。
ありがとうございます。
それでは、【目次4】「育成就労から特定技能へのキャリアパス」の本文をご提案いたします。
読者がステップごとの流れや要件を視覚的・直感的に理解できるよう、段階を明確に分けて説明しています。
4. 育成就労から特定技能へのキャリアパス
3年→5年→無期限へ。必要な条件とは?
育成就労制度の最大の特徴は、制度の“終わり”がゴールではないことです。
3年間の育成期間を経て、一定の条件を満たせば**「特定技能1号」に移行することができ、さらにその先には「特定技能2号」**という無期限在留のステージが用意されています。
これは外国人本人にとっても、「長く日本で働き、生活基盤を築ける」ことを意味し、受入企業にとっても育てた人材を長期的に雇用できるというメリットがあります。
キャリアパスの全体像
- 開始時点:日本語能力A1レベル(JLPT N5程度)または相当講習の受講
- 転籍要件:技能検定(基礎級)+日本語能力の一定レベル達成(例:A2)
- 終了時点:技能検定(基礎級)+日本語能力A2レベル(JLPT N4程度)
- 技能水準:相当程度の知識又は経験を必要とする技能(特定技能1号評価試験、技能検定3級等を想定)
- 日本語水準:A2レベル相当
- 技能水準:熟練した技能(特定技能2号評価試験、技能検定1級等を想定)
- 日本語水準:B1レベル相当
制度開始までに、企業側もこうしたキャリアステップを理解し、支援体制の整備を進めておくことが求められます。
承知しました。以下に、いただいたスケジュールを反映させた【目次5】の修正版をご提案いたします。
「いつ・誰が・何を進めるのか」が分かるように整理し、企業が制度導入の全体像を具体的にイメージできる構成にしています。
5. 今後のスケジュールと制度普及の見通し
育成就労制度は、既に法的枠組みが整備されており、遅くても令和9年中には、本格的な運用が開始される予定です。
特に、現在技能実習生や特定技能外国人を受け入れている企業にとっては、早期に制度を理解し、準備を進めることが重要です。
制度の施行スケジュール(予定)
育成就労制度を定めた「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」は、令和6年(2024年)6月21日に公布されました。
この制度は公布日から起算して3年以内に政令で定める日に施行されるとされており、以下のようなスケジュールで準備が進められる予定です。
年度ごとの主な予定:
| 年度 | 主な内容 |
|---|---|
| 令和6年(2024年) | 基本方針・主務省令等の作成※同年12月に「有識者会議」が設置され、制度設計の詳細を検討 |
| 令和7年(2025年) | 分野別運用方針の策定(例:育成就労の対象産業の明確化)対象職種や分野に関するガイドラインの整備 |
| 令和8年(2026年) | 事前申請の受付開始(管理支援機関の許可申請など)受入れ体制の事前構築が本格化 |
| 令和9年(2027年) | 改正法施行・育成就労制度の運用開始 |
あわせて、令和6年~制度開始時にかけて、対象となる送り出し国との間で二国間取決め(MOC)の交渉・作成・署名が順次行われます。
6. まとめ:受入れ企業が今、押さえておくべきポイント
ここまで、育成就労制度の概要、技能実習制度との違い、制度の仕組みやキャリアパス、そして今後のスケジュールについて解説してきました。
育成就労制度は、これまでの技能実習制度の課題を正面から受け止め、より実態に即した、外国人と企業の双方にとって持続可能な制度として設計されています。
制度の施行は令和9年(2027年)までに予定されていますが、準備はすでに始まっており、今のうちから制度の仕組みを理解し、受入体制の見直しを進めておくことが重要です。
在留資格に関するお悩みは、ビザ専門の行政書士への相談がおすすめ
行政書士事務所ビザハブでは、外国人の在留資格申請を専門として、これまで数多くのビザ取得や企業の外国人材受入れをサポートしてきました。
今回の育成就労制度に限らず、弊所では「ビザに特化した行政書士事務所」として配偶者ビザ・経営管理・特定技能・技術人文国際・永住・帰化など、在留資格に特化した申請サポートを行っています。ビザに関するお悩みがあれば、お気軽にビザハブまでご相談ください。


行政書士 羽野悌慈
行政書士事務所ビザハブの代表行政書士
日本の企業が深刻な人手不足に直面していることを痛感し、大学卒業後に社内起業で外国人材事業を立ち上げる。
外国籍の方々にとって必要な在留資格(ビザ)は、個々の事情に応じて申請の難易度が高いケースが多く、この問題を自らの知識と経験で解決したいと考え、行政書士事務所を開業する。
。


